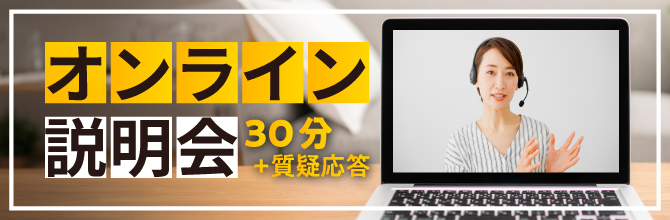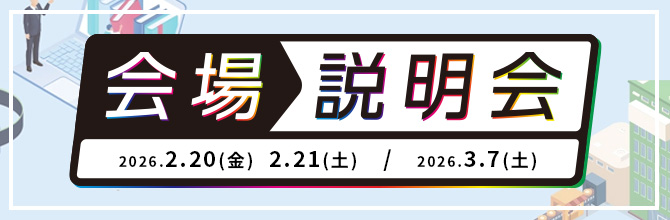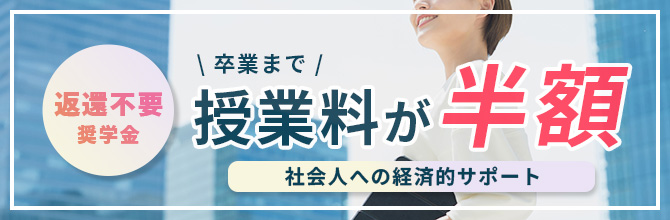「子育てと仕事の両立って、どうしてる?」 そんな、誰もが一度は抱く疑問や悩みを、気軽に話し合える場があったなら…。
育児をしながらサイバー大学で働く教職員が、悩みや喜びを共有し、部署を越えた繋がりを深め、会社としてできるサポートについて考えることを目的に育児座談会を開催しました。
時短勤務で奮闘する方や、育休から復帰したばかりの方、そして子育てが少し落ち着いた先輩パパ・ママまで、さまざまな立場のメンバーが参加。笑いあり、深い共感のうなずきありの、温かい時間となりました。本記事では、当日の様子をレポートします。
第1回育児座談会
「仕事と育児の両立」、「あったらうれしい会社の制度」という2つのテーマでディスカッションしました。

仕事と育児の両立:日々の奮闘と工夫
子どもの成長段階に応じたさまざまな悩みや、それを乗り越えるための工夫が共有されました。
日常的な悩みとリアルな声
「いやいや期」の対応、登園・食事の拒否、こだわりが強くなる子どもとの向き合い方等、幼児期特有の悩みや、「保育園で頻繁に病気をもらってくる」「小学校進学後の働き方がどう変わるのか」といった、少し先の未来に対する関心も高く、活発な情報交換が行われました。
在宅勤務のメリットと課題
多くの参加者から「在宅勤務制度がありがたい」との声が聞かれました。昼休みを利用した夕食の準備や、在宅勤務のおかげで保育園の送迎時間ぎりぎりまで働ける等、柔軟な働き方が両立を支えている実態が浮き彫りになりました。一方で、「仕事と育児のオンオフの切り替えが難しい」という課題も共有されました。
参加者それぞれの工夫
各家庭での工夫として、夫婦で家事・育児の「シフト」を組んで役割分担をしているという話や、病児保育やベビーシッターを利用して乗り切った等、経験談が語られました。特に、病児保育を実際に利用した先輩の話は、他の参加者にとって貴重な情報となったようです。また、子どもの学校とのやり取りでAIを活用し、効果的でより円滑なコミュニケーションを図ったという、サイバー大学ならではのエピソードも飛び出しました。
会社への期待:より働きやすい環境をめざして
教職員がより安心して仕事と育児を両立できる環境づくりのため、会社への具体的な要望やアイディアも多数提案されました。
求められる柔軟な制度
休暇制度の拡充
「時間単位の休暇取得」や、子どものイベント・急な体調不良に対応できる休暇制度への期待が寄せられました。
経済的サポート
ベビーシッターや病児保育の利用料補助、法人契約チケットの配布等、経済的負担を軽減する制度への期待が寄せられました。また、「家事代行サービスは、他人が家に入ることへの抵抗感があり、利用のハードルが高い」という意見に対し、初回利用の補助等、トライアルのハードルを下げる取り組みがあるとチャレンジしやすいとの声が上がりました。
コミュニケーションと企業風土
交流の場の継続
「部署が違うと、相手に子どもがいるかどうかも分からない」「普段、子育ての話ができる場がないので、今回のような座談会は非常に嬉しい」という声が多数聞かれ、部署の垣根を越えてフラットに話せる機会の重要性が再認識されました。
子どもの職場理解
「お仕事見学会」や「キッズ同伴出勤デー」といった、子どもが親の職場に触れる機会を設ける提案がありました。これは、子どもの経験になるだけでなく、教職員同士の相互理解を深めるきっかけにもなると期待されます。
参加者の感想
- 無条件にママ、パパ大好きと言ってくれる期間は意外と短い。ぜひ今を楽しんでほしい。(先輩ママさんから)
- 自分しかできない仕事を抱え込み、深夜まで働いてしまうことがあったが、それが両立の上での課題だと気付くことができた。業務の属人化は、部署全体で考えるべきテーマだと感じた。
- 普段は話す機会のない他部署の方々と情報交換でき、とても心強く感じた。悩んでいるのは自分だけではないと分かり、気持ちが楽になった。
- 子育てしやすいことも含め、周りの人にもやさしい会社だといいなと思う。
まとめ
今回の座談会は、仕事と育児の両立に奮闘する教職員にとって、悩みを共有し、仲間との繋がりを再確認する貴重な時間となりました。在宅勤務という環境を活かしながらも、それぞれが工夫を重ねて日々を乗り越えている様子が伺えました。
フレックスにおける時間単位の休暇取得方法の周知や育児関連サービスの利用促進、そして何よりも教職員同士が気軽に情報交換できる場の設定等、会社として取り組むべき課題も明確になりました。
仕事も家庭も教職員にとってかけがえのない時間です。教職員一人ひとりがその両方を大切にしながら、いきいきと活躍できる環境づくりに努めてまいります。