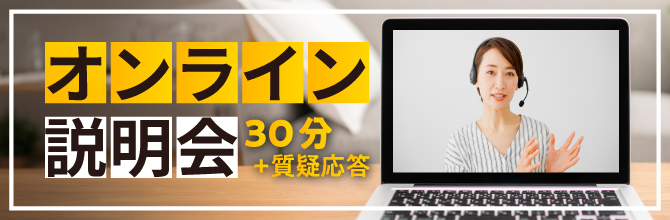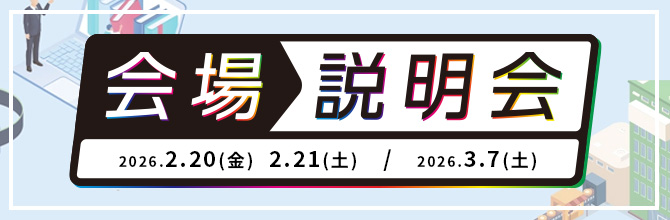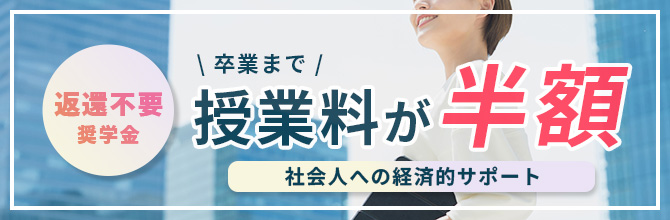「大学卒業率」とは、総人口に占める大卒者の割合を意味します。大卒の学歴があることで、就職・転職やキャリア選択等で有利に働くケースが多いです。しかし、大学卒業率の数値については、意外と正確な数値をイメージしづらいかもしれません。そこで本記事では、日本の大学卒業率や大学を卒業するメリットについて、詳しく解説します。
日本における大学卒業率・大卒者の割合
日本における大学卒業率・大卒者の割合の傾向について、まずは次のポイントから解説します。
- 総人口に占める大卒者の割合は約2割
- 若年層の大学卒業率は約5割と推定できる
- 在学者の男女比は男性がわずかに高い
- 日本の大学卒業率は高まり続けている
- 大学卒業後の就職者の割合は8割弱
総人口に占める大卒者の割合は約2割
総務省統計局が発表した「令和2年国勢調査 ライフステージでみる日本の人口・世帯」によると、日本の総人口における大卒者の割合、つまり「大学卒業率」は2020年時点で23.1%となっています。
この数値は調査を行う度に増加しているため、今後も大学卒業率は高まる可能性があると考えられるでしょう。なお、本調査の「約2割」という数値はあくまで総人口に占める割合であり、後述するように若年層ほど大学進学率は高い傾向があります。
若年層の大学卒業率は5割近い
さらに同調査によると、25~29歳および30~34歳の大学卒・大学院卒の割合は5割近くになっています。また、短期大学や高等専門学校も含めると、25~39歳では6割を超えています。言い換えれば、若年層では過半数が何らかの高等教育を受けているということです。
在学者の男女比は男性がわずかに高い
前述した資料では、大学・大学院在学者に占める男女の割合は、2020年時点で男性54.3%・女性45.7%となっており、男性の比率がわずかに高いです。なお、1980年時点では男性が77.2%・女性が22.8%であったため、大学在学者数の男女差が小さくなりつつあることが分かります。
日本の大学卒業率は高まり続けている
同調査の「15歳以上卒業者の最終卒業学校の種類別割合」項目によると、大学および大学院の卒業率は10年ごとに次のように変化しています。
1990年 | 12.1% |
|---|---|
2000年 | 15.4% |
2010年 | 19.9% |
2020年 | 25.5% |
これは全年齢の大学卒業率であるため、前述した若年層に絞り込んだ数値より低いですが、調査を行う度に大学卒業率が増加していることが分かります。
大学卒業後の就職者の割合は8割弱
大学卒業後の主な進路状況として、就職者が76.5%で、大学院等への進学率は12.6%となっています。従って、大学院等へ進学する場合を除き、大学卒業者の大半が就職を選ぶといえるでしょう。
大学を卒業するメリット
前述したように、日本における大学卒業率は増加傾向にあると考えられますが、その理由として次のようなものが挙げられます。
- 高度な専門知識や教養が身に付く
- キャリアの選択肢が広がる
- 高卒より高い収入が期待できる
- 大学で人脈を広げることができる
高度な専門知識や教養が身に付く
大学に進学することで、専門分野に関する深い知識や教養を身に付けることができます。「大卒」という学位は専門的なスキルの証明になるため、企業や組織からの信頼の獲得や他者との差別化を図ることが可能です。就職・転職の選択肢はもちろん、実際に業務をこなすうえで知識や教養が役立ち、将来のキャリア形成につながるでしょう。
キャリアの選択肢が広がる
企業にはさまざまな求人がありますが、専門知識が求められる職種や高収入が見込めるポスト等は、「大卒の学歴」が条件であることが多いです。大学を卒業することで「学士」の学位が取得できるため、「大卒資格」が条件である求人に応募できるようになります。
また、学位があれば海外で就労ビザを取得しやすくなるため、国外で活躍することをめざす場合にも役立つ等、将来のキャリアの選択肢が広がることが魅力です。
高卒より高い収入が期待できる
一般的には高卒よりも大卒の方が同じ職種でも賃金が高く、より上位の職種にも就きやすいため、大卒資格を取得することで収入アップが期待できます。
実際に厚生労働省の「令和5年賃金構造基本統計調査 結果の概況」によると、学歴別の平均月収は高卒が約28万円である一方、大卒は約37万円となっており、1か月あたり平均で10万円近くもの差が出ます。そのため、キャリアアップや収入アップをめざすのであれば、大学を卒業するのがお勧めです。
大学で人脈を広げることができる
大学生活ではさまざまなバックグラウンドを持つ人と出会う機会があるため、積極的に交流することで人脈を広げることができます。その人脈がきっかけとなり、将来の就労やビジネス等で有利になることがあるかもしれません。自宅学習が基本の「通信制大学」であっても、オンラインで学生同士のコミュニティがあるため、ぜひ活用したいところです。
大学を卒業して学位を取得する方法
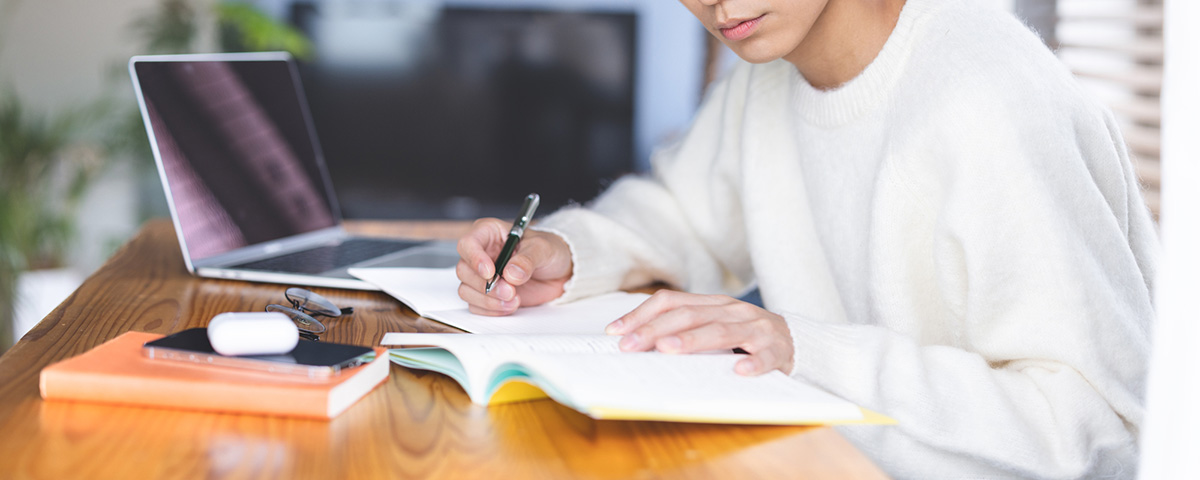
大学を卒業して学位を取得する方法として、次のようなものがあります。それぞれの特徴や注意点等について解説します。
- 大学の昼間学部
- 大学の夜間学部
- 通信制大学
大学の昼間学部
通信制大学や夜間学部が存在しない学部、医師・薬剤師等の一部の国家資格をめざす場合は、昼間学部への通学が必須となります。ただし、一般の4年制大学の学生と同様に、平日は基本的に朝から夕方まで講義に出る必要があるため、仕事や育児等がある場合は通学のハードルが高くなることが難点です。
大学の夜間学部
仕事や子育て等で忙しく、大学の昼間学部に通えない場合は、夜間学部でも大卒資格がめざせます。ただし、講義は夕方ごろに始まり、1回90分の講義を複数受ける必要があるため、社会人の場合は定時に帰宅できなければ履修継続が難しいかもしれません。スケジュール調整ができない場合は、後述する「通信制大学」を選ぶことで、自宅学習で必要な単位が修得できるようになります。
通信制大学
通信制大学もしくは大学の通信教育課程に通い、必要な単位を修得することで、一般的な4年制大学と同様に大卒資格が取得できます。定期的なスクーリング(登校)が必要な場合を除き、自宅で自分のペースで専門的な知識・スキルを習得できます。
ただし、学習スケジュールや履修の管理等を自身で行う必要があるため、自己管理能力やモチベーションの維持が欠かせません。一方で、居住地やスケジュール等の理由で一般の4年制大学に通えない場合でも、自宅で学びながら大卒資格の取得がめざせることが大きな魅力です。また、学生同士のコミュニティもあるため、モチベーションを高めながら学べるでしょう。
後悔せず卒業するための大学の選び方
大学を卒業するためには、次のようなポイントを意識して「自分に合う大学」を選ぶことが大切です。
- 学習内容やカリキュラムが自分に合うか
- 無理なく通学や履修を継続できるか
- サポート体制や学習環境が整っているか
学習内容やカリキュラムが自分に合うか
大学を卒業するためには、4年間学び続けて単位を修得する必要があります。そのため、「本当に学びたいこと」でなければモチベーションが続かず、途中で退学せざるを得なくなってしまうことがあります。
大卒の学歴、つまり「学士」の学位は大学を卒業しなければ取得できないため、常に学び続ける意識を持つことが大切です。学習内容やカリキュラムが自分に合うことを確認して、「4年間学んで卒業できる」と思えるような大学を選びましょう。
無理なく通学や履修を継続できるか
通学が必要な大学に入学する場合は、自宅から通いやすい場所で、なおかつ自身の生活スケジュールの範囲で履修を継続できることも重要なポイントです。「大学が遠い」「生活スタイルと合わない」等の場合、通学の負担が大きくなるため、卒業することが困難になってしまうかもしれません。
自宅の近くに大学がない、もしくは仕事や育児等のスケジュールの都合で昼間学部に通学できない場合は、「通信制大学」がお勧めです。
サポート体制や学習環境が整っているか
大学の学習内容は専門的で難易度が高いため、疑問点や不明点が生じたときに解決できなければ、卒業が困難になってしまいます。特に通信制大学では自宅学習が基本なので、分からないところを解決できるようなサポート体制や、効果的に学習できる環境が欠かせません。
例えば「サイバー大学」では、教職員が卒業までしっかり並走してくれるため、2学期目履修継続率が2024年10月時点で90.5%と非常に高い水準にあります。学生が学習を継続しやすい環境が整っており、安心して大学卒業をめざすことができるでしょう。
大学を卒業して学位を取得するなら「サイバー大学」へ
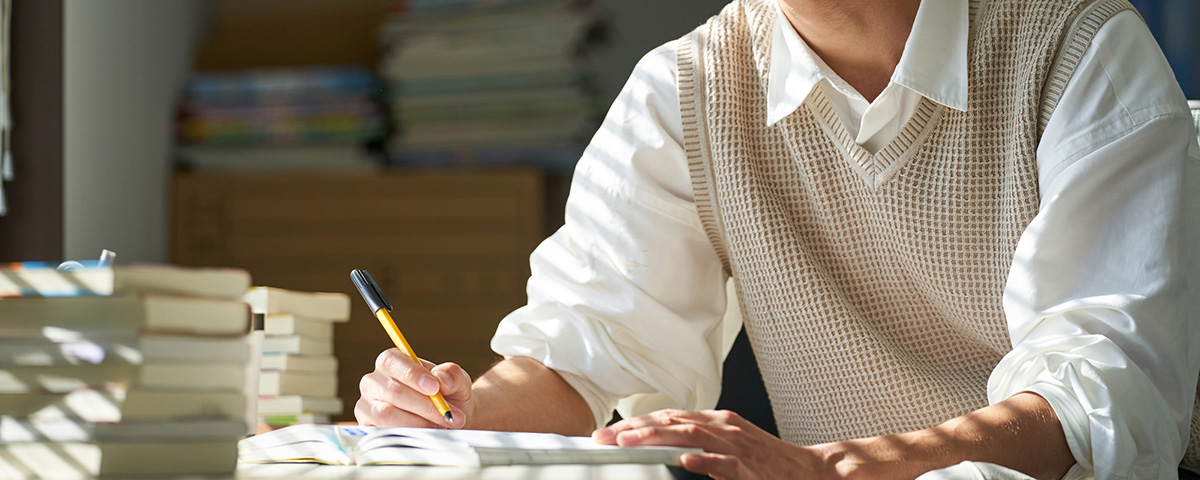
日本における大学卒業率は、全年齢では約2割・若年層では5割近い水準になっています。大学を卒業して大卒の学歴を取得することで、高度な専門知識や教養が身に付き、キャリア選択の幅がこれまでより広がります。
大学を卒業するためには、無理なく通学や履修を継続できる大学を選ぶことが大切です。居住地やスケジュール等の関係で一般的な4年制大学に通うことが難しい場合は、自宅に居ながら高等教育が受けられる「通信制大学」がお勧めです。
通信制大学の「サイバー大学」では、フルオンラインの大学でスクーリングが不要なので、全国どこでも、海外(※GDPR加盟国以外)からでも学ぶことができます。学修支援はもちろん、進路選択や卒業後のキャリア形成のサポート等も充実しており、就職・転職の幅が広がるでしょう。
さらに、学生や教職員が参加する公式コミュニティがあるため、同年代はもちろん異なる世代の学友との交流の機会が得られて、人脈が深まることも魅力です。学歴や大学の学位等に関してお悩みの方は、この機会にぜひサイバー大学を検討してみてください。