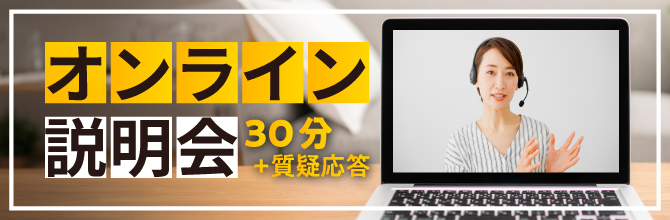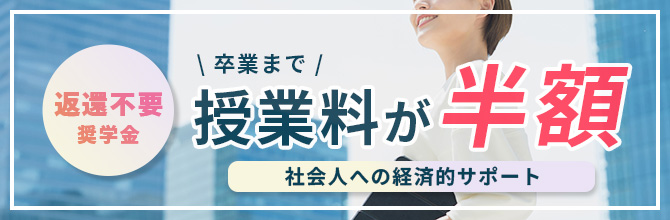近年、継続的な学修や社会人の学び直しの注目度が高まるにともない、リカレント教育が国を挙げて推進されています。とはいえ、リカレント教育とは具体的にどのようなものかよくご存知ない方も多いのではないでしょうか。
この記事では、リカレント教育の意味や推進の背景、日本における現状と課題を簡単に解説します。見分けがつきにくい「生涯学習」および「リスキリング」との違いも分かりやすくまとめました。リカレント教育を実践する際のポイントも紹介しますので、スキル・キャリアアップを志す方はぜひ参考にしてください。
リカレント教育とは
まず、リカレント教育とは何か、具体例や推進の背景、国内における現状と課題を踏まえてご説明します。
リカレント教育の意味
そもそも「リカレント(Recurrent)」とは「繰り返す・循環する」ことを意味する言葉です。従って「リカレント教育」を簡単にいうと、各々のタイミングで就労と教育のサイクルを繰り返しながら、生涯にわたって自律的かつ主体的に学び続けることを指します。
リカレント教育の具体例
リカレント教育の具体例を簡単にいうと、各種学校を卒業して教育から離れた後も仕事に必要な能力やスキルを磨くために学び続けることです。2021年に経団連がまとめた調査結果では、リカレント教育に求められる学びの内容でもっとも多いのは、実務に必要な専門知識や技能の習得でした。
なお、デジタル社会において求められるシーンの多い資格として、以下のような例が挙げられます。
- プログラミング関連の資格
- ITパスポート
- ITストラテジスト
- 情報処理技術者試験
- 情報処理安全確保支援士試験
- 第四次産業革命スキル習得講座認定制度(AI・loT・ロボット・ナノテクノロジー・バイオテクノロジー等)
社会人の学び直しの講座や支援制度に関する情報は、文部科学省が運営する「マナパス」に幅広くまとめられていますのでチェックしてみてください。
リカレント教育が推進されはじめた背景
もともと、リカレント教育はスウェーデンの元首相であるオロフ・パルメ氏が、教育大臣に就任していたときに提唱した概念です。その後、1969年の第5回ヨーロッパ文相会議で発表され、1970年代からOECD(経済協力開発機構)によって世界中に広められることとなりました。
日本においては、人生100年時代の到来とともに労働環境や考え方が多様化し、職業人生が長期化したことによりリカレント教育の重要性が高まっています。くわえて、社会のDX化が進展し、デジタル分野における社会人の学び直しが重要視されていることもリカレント教育が注目される一因です。
2020年にはリカレント教育支援の強化方針を盛り込んだ「成長戦略実行計画案」が閣議決定され、厚生労働省・経済産業省・文部科学省等が連携して支援に取り組むようになりました。また事業主からも、ES(従業員満足度)向上および人材流出防止対策として注目されています。
日本におけるリカレント教育の現状と課題
現在の日本において、リカレント教育はまだ浸透しているとはいえません。従って、リカレント教育に関する支援制度の拡充が重要な課題のひとつとなっています。
内閣府の調査によると、日本におけるリカレント教育はOECD諸国と比べて大きく後れを取っているのが現状です。また、厚生労働省が発表した調査結果で、令和3年度の教育訓練休暇制度や教育訓練短時間勤務制度の利用者がいずれも2%以下にとどまっていることからも分かる通り、労働者の負担が大きくなっています。くわえて、リカレント教育で学び直したことが、給与アップや昇進等の形として反映されないケースも珍しくありません。
とはいえ教育訓練休暇制度や教育訓練短時間勤務制度等により助成金が給付されることもあり、最近は社員教育の一環としてリカレント教育を導入する事例も増えてきました。今後、労働者および事業主に対する学び直し支援制度をよりいっそう拡大・周知していくことが求められています。
リカレント教育の類似ワードとその違い

リカレント教育と似た用語として「生涯学習」と「リスキリング」というワードがあります。それぞれ異なる意味を持ちますので、違いを正確に把握しておきましょう。
リカレント教育と生涯学習の違い
リカレント教育と生涯学習で大きく異なるポイントは、学びの「目的」です。
生涯学習とは、より豊かで充実した人生を送るための学びを指します。1965年に、ユネスコ(国際連合教育科学文化機関)の成人教育長だったポール・ラングラン氏によって提唱されました。趣味や生きがい、仲間作りのほか、健康増進等のさまざまな活動が具体例であり、リカレント教育より定義が幅広いことが分かります。
一方、リカレント教育は生涯学習の考え方を基にしつつ、特に「就業人生」に焦点が当てられている概念です。つまり、業務の円滑化やさらなるキャリアアップ、より長く働き続けることを目的とし、就業に関わる知識・スキルの習得に重きが置かれています。
リカレント教育とリスキリングの違い
リカレント教育とリスキリングの違いは「学びの主体の所在」です。
「リスキリング(Re-skilling)」とは、業務遂行に関するスキルを習得することを指します。主な定義はリカレント教育と同じですが、リスキリングは従業員の育成を目的とする企業主導の取り組みです。デジタル社会の進展により多様化するニーズに対応するため、人的リソース強化戦略の一環としてリスキリングによるスキルアップ支援が行われています。
対して、リカレント教育における学びの主体は労働者であり、学修のタイミングも人ぞれぞれです。個人が任意で学修の必要性を判断し、各々のペースで学びを進めます。
リカレント教育で得られるメリット
労働者にとってのリカレント教育のメリットは、主に次の3点です。
- 企業への貢献度が上がる
- ビジネスパーソンとしての価値が高まる
- キャリアアップにつながる
企業への貢献度が上がる
リカレント教育によってスキルアップすれば、業務効率がアップし、結果的に企業の生産性の向上やDX化に貢献できます。各分野の専門性が磨かれ、よりよいサービスの提供が可能になるでしょう。
ビジネスパーソンとしての価値が高まる
リカレント教育で学び直して自らの強みを作り出せば、企業が確保しておきたい人材となり、長期的に勤められる可能性が上がります。また、もし何らかの理由で退職することになっても、次の就職先が見つかりやすいのも大きな利点です。
キャリアアップにつながる
継続的な学修が、労働者のスキルアップや今後のキャリア形成に及ぼす影響は小さくありません。リカレント教育によって対応できる業務の幅が広がれば、就業意欲も高まり、より広い視野で今後のキャリアを考えられるようになるはずです。
リカレント教育を効果的に実践する3つのポイント

リカレント教育の効果を最大限に活かすためには、事前に以下3つのポイントを確認しておきましょう。
- 企業・組織とビジョンを共有する
- 学び直しのためのリソースを確保する
- 大学や専門学校の講座を活用する
企業・組織とビジョンを共有する
リカレント教育を実践しても、就業を希望する企業・分野と学びの方向性がずれていては意味がありません。自らに求められる役割を正しく理解し、企業の意向とすり合わせたうえで、必要な知識やスキルを学ぶことが大切です。
学び直しのためのリソースを確保する
リカレント教育の実践には、時間的・経済的なリソースが不可欠です。企業からのサポートや配慮が得られない場合は、公的支援が受けられないか検討してみましょう。例えば、リカレント教育に関する公的支援には以下のようなものがあります。
公的支援の種類 | 対象 |
|---|---|
ハロートレーニング(公的職業訓練) | 雇用保険に加入している方 |
キャリアコンサルティング | 在職中の方 |
教育訓練給付制度 | 対象講座を修了した方 |
高等職業訓練促進給付金 | 対象の国家・民間資格の取得のために修学するひとり親の方 |
特定支出控除制度 | 特定支出の合計額が基準額を超える方 |
上記の支援は、すべて申請により無料で受けられます。地域によって内容や期間が異なるサービスもあるため、自治体の窓口に相談してみてください。
大学や専門学校の講座を活用する
リカレント教育は大学や専門学校、通信教育等で受けるのがもっともお勧めです。専門学校や大学では、学生以外でも履修できる各種講座が開講されています。オンラインで受けられるリカレント教育もあり、働きながら学び直すことも可能です。また大学・専門学校等では、リカレント教育の履修に関して、以下のような証明制度が設けられています。
- 履修証明制度
- 職業実践力育成プログラム(BP)認定制度
- オープンバッジ制度
上記のほか、大学・専門学校によっては独自の証明・認定制度が設けられている場合もあります。なお、サイバー大学では日本初のマイクロクレデンシャルを取り入れた学位プログラムを導入しており、その学習歴を証明する「オープンバッジ」が取得可能です。自らの学修歴やスキルを可視化できるため、その後のキャリアアップや転職・就職に有利に働きます。
リカレント教育でITを学ぶならサイバー大学へ!
生涯にわたって自分らしく働き続けるためには、主体的に学び、自らステップアップしていこうとする姿勢が不可欠です。リカレント教育で幅広い知識やスキルを身に付ければ、自らの価値や希少性が高められます。就労による自己実現のためにも、企業にとって魅力的なビジネスパーソンをめざしましょう。
「サイバー大学」は、リカレント教育にチャレンジしたいすべての方を全力で応援します。目的に合わせて継続して学べるマイクロレジデンシャル制のカリキュラムと、通学不要の完全オンラインによる授業形態を採用。ITとビジネスをかけ合わせた実践的な内容を自分のペースで身に付けられます。在学中はもちろん、卒業後のサポートも充実。この機会にぜひ資料請求のうえ、本学の魅力をご確認ください。